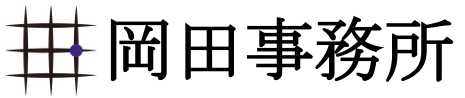日経電子版で保存した記事(2024年12月)

日経電子版で保存した記事の中から、ここ最近で気になったものを紹介し、私の考えや連想したことを書いてみます。
〈多様性 私の視点〉日本の社長、任期なぜ短い?
日本経済新聞2024年11月25日
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85006170U4A121C2TYA000/
「ダイバーシティが日本企業で進まない背景の深因には、実は日本企業の不十分なコーポレートガバナンスもある」と指摘しています。多様性はきれいごとではなくて、事業を存続させるためのイノベーションを生み出すのに必要なもの。まずは取締役会の多様性を担保し、業務執行を監督する仕組み作りが求められます。
私はある顧問先で社外取締役に就かせてもらっていて、時に経営者には煙たがられるような苦言も呈してきました。それでお役御免となるのであればそれまでのことと割り切っていて、業務執行に携わる取締役の監督を名実ともに果たしているつもり。就任して8年目を迎えているので、それなりに機能していると認めてもらえているのでしょう。
若者の飲酒文化と談論風発
日本経済新聞2024年11月28日
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85082260X21C24A1DTC000/
先日、高校の部活の先輩とお会いする機会がありました。私より9個上だそうで、当時の活躍の様子は「伝説」として語り継がれている先輩です。私も高校時代から飲酒の機会はありましたが、この先輩よりさらに上の世代ともなると部活の帰りに居酒屋へ繰り出すこともあったそう。サラリーマンと変わりません。今では考えられない高校時代でした。
いつからか後輩たちと飲みに行く機会も減り、ましてや未成年が同席することも完全に無くなりました。そもそも自分自身がすっかり飲まなくなっています。酒は百薬の長というのは迷信。たまには楽しく飲むこともありますが(先日飲んだばかり)、基本的にはまったく口にすることがなくなってしまいました。時代が変われば文化も変わるものです。
〈信用調査ファイル〉立ち枯れた園芸新興
日本経済新聞2024年12月3日
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85191090S4A201C2TB1000/
「政府は22年を「スタートアップ創出元年」と位置づけ育成強化に乗り出しているが、支援頼みで生き残れるほど経営環境は甘くはない。生命線はあくまでビジネスモデルの革新性とそれを資金調達につなげる自助努力だ」と結ばれている記事。自助努力が必要だというのは中小企業支援に携わる者としてまったく同感です。
支援者によって支援のスタイルはさまざま。私はベタベタと支援にならない支援らしきことをするのを徹底的に避けています。例えばネットで調べられることを代わりに検索して教えたり、書類の作成を手伝ったりすることはありません。見込客リストを作成するなんてことも、事業者自身が作業するように強く促しています。知恵とアイデアは提供しますが、その後は経営者次第。行動し、成果をつかみ取るのは経営者の役割です。
三越伊勢丹HD社長「百貨店要員さらに縮小」
日本経済新聞2024年12月5日
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85247130U4A201C2TB3000/
以前に百貨店の開店と同時にスーツ売り場に行きましたが、私のお目当てのショップの販売員はバックヤードにいるのか、姿が見当たりません。他のショップの販売員に声を掛けるわけにもいかず、買い物をあきらめてしまいました。本来であれば百貨店の社員が開店から閉店まで販売に責任を持つべきなのに、いつからか出入りの業者に販売を任せきりになってしまっているのです。
私がかつての家業に就職し、最初に配属されたのは日本橋三越の和食器売場でした。当時から百貨店の社員が減り続けていて、その割にあれこれ指図してくるのでよくやり合っていたものです。当時の社員さんたちとはよく飲みに行ったり、楽しくお付き合いもさせてもらいました。皆さん、お元気なのかなとふと気になりました。

息子を抱っこして散歩したコースです
(竹内謙礼の顧客をキャッチ) 豆菓子、ライブではじける
日本経済新聞2024年12月16日
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85446000T11C24A2HF0A00/
大阪にある豆菓子メーカーのライブコマースが評判だという記事。スマホ一台あればどんな発信も可能な時代になりました。あとは自分が一歩を踏み出すかどうかだけ。最初のうちに失敗し、恥をかいた人だけが発信のメリットを体感することが可能です。
情報発信は多くの事業者が必要性を理解しているものの、継続できていないところがほとんどです。メリットを体感できる前にあきらめてしまっているわけで、だからこそ継続できればそれだけで競合に差を付けることが可能になります。
京のいけず、あえて浴びまひょ。
日本経済新聞2024年12月18日
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85523840X11C24A2HF0A00/
父までは代々、京都で生まれていて、私が初めて東京で生まれました。京都の人からすると「京都から出て行った家の人」のように見られていますし、東京の人からすると「東京に越してきたばかりの京都の人」のように見られてきました。
私が京都で暮らしていたのは、これまでのところたったの5年余り。例えば、繁華街で散々飲んだ次の日に、「昨日は楽しそうに飲んでいましたね」と声を掛けられてギョッとした経験があります。東京生まれの私からしたら、その時に声を掛けてよという感じ。これが京都人のいけずなのかどうかは今でもわかりません。
ポッドキャスト「茶わん屋の十四代目 商いラジオ」を毎週金曜日10:00に配信しています
関連記事