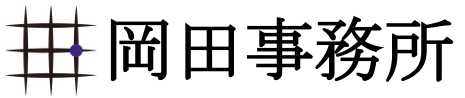ひらがなが難しい
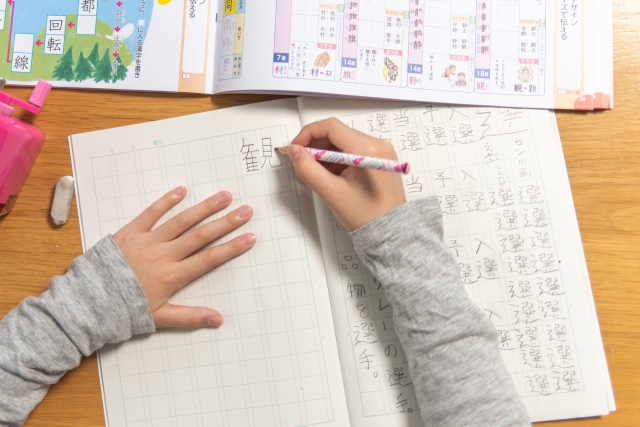
夏休みが終わりました。高校生の息子の宿題が終わったのかどうか気になっています。課題や宿題について書いてみます。
9月の課題が送られてきた
オンラインペン字講座の9月の課題が送られてきました。基本的に何を書いて送っても先生が添削してくださるのですが、最近は先生が課題を考えて送ってくれます。今月の課題のひとつが「おにやんま とんぼ こおろぎ」。ひらがなの楷書でシンプルなもの。どうやら小学一年生レベルの課題だそうです。ところがいざ書き始めてみると、難しい。ひらがなだからとさらっと書き始めてみたら、思いのほか手間取ってしまいました。
ひらがなの何が難しいかというと、私の場合、なかなかまっすぐに書けないのです。まっすぐに書いたつもりでも、後から眺めてみると「に」がバランスが悪く横にズレているような感じ。今回も書き上げた時点では自信があったのですが、先生からは書き直すようにとのご指示。シンプルなひらがなではありますが、私にとっては難しい課題です。たまにこうしてひらがなの課題が送られてくると、基礎の基礎があやふやな私の底の浅さが露呈してしまいます。
反対に行書の方が私にとっては書きやすく感じます。先生のお手本を真似すればいいのでなんとなく書けてしまうのです(あくまでなんとなく)。
経営者に宿題を課すことがある
基本的に経営者さんとはその場での対話を展開するようにしていますが、ごくたまに事前に宿題を課すことがあります。いつまでも同じ問題を抱えているような経営者には、宿題をきっかけに課題を乗り越えていただこうという趣旨です。
最近、ある経営者に出した宿題は数字に関するもの。「数字は苦手」と言い放ってしまっていて、会社のお金の流れを把握しようとしていませんでした。事業を営むということは手元のお金を膨らませていくゲームをするようなもの。いつまでも数字を苦手にしていてはそもそものゲームが成り立たなくなってしまいます。
この経営者へは、月々の固定費の額、固定費の何か月分の現金を保有しているか、前期の営業キャッシュフローなどを把握しておくようにお願いしました。経営者を務めているのであれば、規模の大小に関係なく当然把握しておくべき数字です。わざわざ私が提示しなければ、実態を把握しようと行動してくれないように思われたので宿題という形を取らせてもらいました。
こうした宿題を課しても手を付けてくれない経営者もいらっしゃいます。ある事業者の資金繰りが行き詰まりつつあるようだったので、資金繰り予測表の作成をお願いしたことがあります。いついくら足りなくなるのかを円単位で把握してもらうためには、資金繰り予測表を自ら手を動かして作成するのが一番。漠然と「〇月頃に〇百万円足りなくなりそう」などという解像度では、経営者自身が怖くてしょうがないはずです。
ところが、資金繰り予測表が作られることはありませんでした。どうやら実態を目の当たりにするのが怖いようでした。せっかく改善のきっかけにして欲しかったのに、事態が好転することなく廃業を余儀なくされました。

小学生と同じ勉強をしています
適度な課題が刺激を与えてくれる
今朝、自宅のエレベーターで一緒になった小学生に「宿題終わってるの?」と尋ねたら、「完璧に終わっている」と答えてくれました。我が家の息子は小学校の時から夏休みが終わっても宿題に取り組むのが当たり前だったので、思わず感心してしまいました。そういえば自分が学生の頃も、適当な宿題は隣の席の女の子に写させてもらっていた記憶があります。親子で宿題には振り回されているようです。
大人になると宿題を課されることがほとんどなくなります。何を課題として、どのようにやっつけるかは社会人としての裁量に任されることに。仕事に限らず課題から刺激を得られなくなるというのはもったいないことです。一生学び続けなければいけないのと同様に、自分へ課題を与え続けなければいつしか錆ついていってしまうのではないでしょうか。私の朝はオンラインペン字講座の課題を書くことから始まります。朝から集中するとその日一日の過ごし方も変わってくるように体感しています。
自分から進んでちょっとした課題にぶつかっていけば、社会人としての鮮度を(少しは)保つことができると考えています。
関連記事