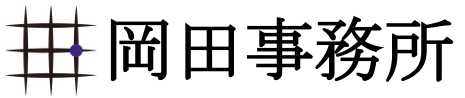組織を去るときのあれこれ

ある関与先との契約を解約することが決まったので、後任のために引継書を作り始めています。私が着任した時には引継ぎらしい引継ぎがなく、困惑したものです。
関与先の後任のために引継書を作り始めている
9月から働き方が変わるので、関与先によっては後任のために引継書らしきものを作り始めています。事務職ではないのでいわゆるマニュアル的な要素はあまりなくて、どういった立ち位置で働くことになるのか、どういった気配りが求められるのか、業務の軽重についてなど、もし私が着任するのであれば真っ先に欲しい情報を盛り込んだものにします。
今回、ゼロから引継書を作らなければいけないのは私の前任が引継ぎらしい引継ぎをしなかったから。着任前に挨拶程度の打ち合わせはありましたが内容が乏しく、メモを取る機会さえ無かったレベルです。さらには名刺は全部破棄されていました。後から聞いたところ、ご本人が希望した契約延長に関するゴタゴタらしきものがあったそう。そうした前任者の後を受けて働き始めた経験があるので、今回、後任に引き継ぐに当たってはきちんと引継書を残して差し上げようと考えているわけです。
着任した当時、何から手を付ければ良いかまったくわからず途方にくれました。個人事業主として受けている仕事なので返上しようかと考えたくらい。それでも周りの環境に恵まれてこれまでやってこれたので、引継ぎをするのは当たり前のことです。世の中にはとんでもない社会人というのがいくらでもいます。社会人人生の前半を同質性の高い家業という温室で歩んだ私は、今でもたまにびっくりするようなことに出くわしてしまいます。
家業の代表取締役を退任したとき
2015年に家業の代表取締役を退任した時、投資ファンドが選んだ新社長とは引継ぎらしい引継ぎはありませんでした。この場合はこれで良かったのだと思っています。社名は存続しましたが、資本も経営も変わるまったくの新会社でのスタート。旧体制の経営者が何かをお伝えできることなどありませんでしたし、彼ら彼女らも耳を傾ける必要はなかったでしょう。
雇われる立場の人々と違って、経営者は過去に責任を持ちつつ、未来を切り拓いていくのが仕事です。そこに定型的な業務は存在しません。マニュアルや引継書などは不要のはずで、無ければないでどうにかなるものなのです。
そういえば家業で父から事業承継した際も引継ぎはゼロでした。メイン銀行から遠回しに促されての事業承継でしたが、あまりにもあっさりと十四代目に就任してしまったことを覚えています。業績が窮迫しつつあったので就任披露パーティなどももちろんなし。まずは過去の取締役会の議事録を読むことから社長業を始めたことを覚えています。

花束をもらうのが苦手です
花束を渡すか渡さないか
ある顧問先の経営者と対話をしていた際に、問題従業員の去就について話題になりました。経営者が面談をした結果、本人から退職を申し出てきたそう。そこまでは良かったのですが、後から問題従業員が他の従業員をそそのかすような形で退職者が続いてしまったということでした。
もちろん経営者にとってはおもしろくない事態ですが、私はいかなる事情であれ、「辞める」と口にした従業員を引き留めることには反対だとお伝えしました。幸い、採用にはそれほど苦労していない会社でしたので、退職者の補充も現場の負担にはならなかったそう。
一度でも組織を離れると考えた従業員はいずれ近いうちに会社を去って行くものです。無理に引き留めたところで他のトラブルを招き寄せることにもなりかねません。であるならば、経営者にとってはおもしろくないことなのでしょうが、ぐっとこらえて花束を渡し円満に送り出す方が会社にとっては前向きな結果になるはずなのです。
そういう私は退職時のセレモニーのようなものが苦手です。行政の外郭団体に勤めていた際には、最終出勤日の前に「花束等はくれぐれもお気遣いありませんように」とお伝えしておいたのに何人もの方からいただいてしまったことがあります。事業者さんが持って来てくださった花束はうれしかったのですが、いろいろあった人からいただく花束は複雑なものでした。だから要らないと言ったのに。
誰かが組織を去る時にはあれこれ起こりがちです。必ずしも円満にすべてを整えられるわけではないでしょうが、せめて本人の希望に添った形で送り出すのが良いのではないかと思います。
関連記事