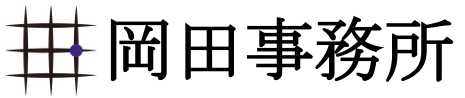組織は戦略に従う

今日は日曜日なので最近考えていることを思いつくままに書いてみます。
荷造りを続けている
引越の日が近づいてきたので少しずつ荷造りを始めています。一気にしてしまうと段ボールの置き場がないので、断続的に買い集めてきて散らばっている日用品などを詰めることから始めています。難しいことは考えずにただ段ボールに放り込むのみ。単身赴任なので家族の荷物を分ける必要はありませんし、物量もたかが知れているからです。
最大20箱と予想していて、今のところ5箱まで終わっています。おそらく12箱くらいで済みそうな雰囲気です。アマチュア無線とお茶の道具類をどこまで持っていくかで変わってくるでしょう。アマチュア無線はまずはトランシーバーだけ持っていくのか、すべてを持って行ってしまうのか悩んでいます。どこでも熊が出そうなので、低山ハイキングと組み合わせて無線遊びが出来るのか心配になってきています。茶道は自主練習を続けていないとあっという間に全てを忘れそうで、教本の他に手持ちの道具類を持っていくつもり。先生の期待を良い意味で裏切らないといけません。
荷物を出すのが11月2日で、現地で受け取るのが8日。8日に一人で作業するのが寂しいかなぁと思い出していて、部活の後輩でも呼びつけてしまうかもしれません。でもそうするとその後に飲みに行くことになるのが確実。翌日の納車に影響が出そうなので、一人で作業することにした方が良さそうです。
中小企業支援とは
某公的支援機関に関する記事が日本経済新聞に出ていました。こうした支援機関をうまく踏み台に使って、今より良い人生を実現して欲しいと願っています。一方で気を付けなければいけないのが、支援に携わる者の心の持ち方。事業の主役はあくまで事業者であって、支援する側は必要な情報を提供するのみの立場です。時に先生などと呼ばれることもあるので、経営者よりも偉いと勘違いしてしまう人が発生しがちなことに心を痛めています。
さらに言うと、支援する側の言う通りに行動したからといって成功が確約されるわけではありません。公的支援機関に所属する専門家(らしき人々)のアドバイス通りに経営しても、誰もがトヨタやユニクロのような事業を生み出せるわけではないのです。結局、不確かな未来に向かって決断できるのは経営者のみ。そもそも行動するかどうかは経営者次第なのです。
支援する側に過度のスポットが当たるというのは決して健全なことではありません。記事は某公的支援機関に非常に好意的な内容でしたが、もしこれから相談に行こうとする経営者がいるのであれば、提供される支援内容の実質実態を見極め、行動し成果を掴み取るのは自分しかできないことだと認識した上で足を運んでもらいたいです。

コンビニで売っている紐が縛りやすいです
組織は戦略に従う
「組織は戦略に従う」とは経営学者のアルフレッド・チャンドラーの言葉だそうです。ではそもそも戦略が存在しなかったらどうなるのか?さらにビジョンや経営理念などと呼ばれる立ち戻る基軸が存在しなければどうなるのか?
私は顧問先の経営者に対し、「10年後を想定して経営してください」と申し上げることがあります。多くの経営者が目先の売上にばかり囚われ、従業員と同じ目線で時間を消費していることに危機感を抱いてしまうからです。
ある経営者は10年後には確実に既存事業が消えてなくなるだろうと断言します(私も同意見)。それなのに気がつくと既存事業の売上がどうとかこうとかそんな話ばかりをしていて、次の事業の柱を築くための取り組みを後回しにしがちです。既存事業が消えてなくなるという見たくも無い現実から目をそらしているだけで、私はいつも「既存事業は従業員に任せて、10年後に向けて新しい事業の種を蒔いてください」とお尻を叩いています。
数字の話も同じ。利益は事業を存続させるために絶対に必要ですが、といって数字だけを見ていても売上が増えることはありません。会議でねちねちと数字をいじっていても、現場でお客様に選ばれることには直結しないのです。なぜその数字を求めるのか、という説明をするのが経営者の役割。足りない数字を詰めるのでは無く、数字を実現することでビジョンや戦略がどのように実現するのかを語らなければいけないと信じています。
関連記事