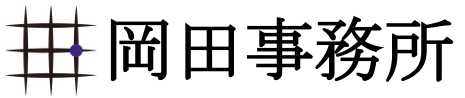顧問先の従業員とどう向き合うか

中小企業支援家として活動していると経営者とはもちろん、従業員とも関わることがあります。顧問先の従業員さんとどのように向き合っているかを書いてみます。
会議に出席することもある
先日、ある顧問先の営業会議に出席させてもらいました。数か月に一度こうした機会があり、ずけずけと意見などを発言しています。
誤解を恐れずに言えば、私は会議(らしきもの)が大嫌いです。何かの方針を決定するのが本来の役割のはずなのに、単なる報告で終わってしまったり、役職者へのアピールの場になっていたりすることが多いからです。さらには長時間拘束されることがほとんど。時間の使い方という観点からもできれば避けたい業務の一つです。
その営業会議は案の定、会議というよりは情報共有の場でした。わざわざ会議のような体裁を取らなくても、日常業務の中で情報共有できないものなのかと疑問に感じてしまいました。このあたりは要改善。当たり前のように会議を定例化することなく、見直しをし続けることが必要でしょう。
さてその会議では社外の立場からいろいろ質問させてもらいました。正確には質問のように見せかけて進行役へ援護射撃をしていたのですが、これがまったく伝わらなかったよう。社外の私からあれこれ尋ねられるのが不快に思われてしまったようで、私の聞き方が悪かったかなと反省しています。
経営者さんとは訪問日によくお話しすることはあっても、すべての従業員さんとまでお話しする機会はなかなかありません。そうなると私の会社への向き合い方などが理解されていないことも起こりうるわけで、従業員さんとの対話には細心の配慮が求められます。
ハラスメントを目撃したらどうするか
ある会社へ訪問していた時、経営者が従業員へずいぶんときつく当たっている場面に出くわしてしまったことがあります。はっきり言えば、パワーハラスメントです。その場で介入するほどのレベルではないと判断したので、経営者に注意をしたのは従業員が退席してから。私にそんなことまで言及されてさぞ気分が悪かったでしょうが、その場では耳を傾けてくれたように思えました。
私の場合、ハラスメント関連の事案に関してはその場での注意に留まらずフォローをするようにしています。例えばセミナーを企画して参加を促したり、パワハラ研修の仕組化を手伝ったりまでするのです。この会社でもあるセミナーへの参加を促し、経営者に出席してもらいました。
中小企業支援家というと経営者と話す時間が圧倒的に多いわけですが、時にこうして従業員を守るために立ち回らなければならないときも発生します。すべては会社が今より良くなり、事業の持続可能性を高めるために取り組んでいることです。

会議は短ければ短いほど良いと考えています
従業員を信じない経営者
ある経営者は自社の従業員を信じ切れていないようでした。「チャンスを与えたのに結果を出さない」「何をしても良いと言っているのに行動しない」といった感じ。私からしたら従業員がどう仕事したかは経営者の責任です。まるで自分だけが正しくて、従業員のレベルが低いかのような発言には違和感を覚えました。
またその経営者は従業員への接し方にも問題がありました。ひとつひとつのやり取りに底意地の悪い感じが付きまとうのです。口では「従業員は家族」「雇用は絶対に守る」などと言っていましたが信じていないのは明らか。そんな経営者のことを従業員は煙たがっていて、会社は崩壊寸前のように思われました。その後、どうなったかは知りませんが、経営者がよほど心を入れ替えないと日々の営業すら覚束なくなっているのではないかと思っています。
経営者となればこの世の中で起こることのすべては自分の責任です。会社の前の信号が赤に変わるのも、従業員が思うような成果を出してくれないのもすべて経営者の責任。まずはこの開き直りとでも言えるような境地に至らないと、従業員と同じ方向を向くことはできません。
ちなみにこの会社の従業員さんと私は非常に良好な関係だったと思っています。最初は社長の意を受けたスパイかなにかと勘繰られたようですが、何度も話しているうちに害をもたらさない存在と認識してくれたようです。中小企業支援家だからといってどのような状況でも経営者の肩を持つわけではありません。会社を良くするためには経営者にお灸をすえることもあるのです。
関連記事