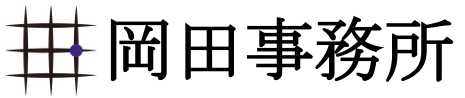持ち上げる

昨日の飛行機で、重たい荷物を持ち上げようとしている人がいました。そんなに苦労するなら、預けてしまえば良いのにと思ってしまいました。
飛行機の中へ持ち込む荷物
昨日・一昨日と、ひいきの野球チームの応援へ出かけてきました。誰かの引退試合になるかもと思って早めにチケットを取っていたのですが、結局ただの消化試合。しかも、しっかり負けてしまい、悔しい思いで帰ってきました。今季は7試合くらい観に行ったはずですが、勝てたのは1回だけ。親子でとぼとぼと帰路につくのがお約束になってしまいました。
帰りの飛行機の中で気になったのが、大きな荷物を持っている人の振る舞いでした。いかにも重そうなキャリーケースを腕をプルプルさせながら持ち上げようとしていて、最初は見守っていた客室乗務員さんが最後にほんの少しだけ手を貸していました。
そんなに重い荷物なら預けてしまえばいいのに、と考える私は心が狭いのでしょうか。客室乗務員さんもいちいち荷物を上げるのを手伝っていたら、飛行機が飛ぶ前に腕が棒になってしまうことでしょう。さっさと家に帰りたい気持ちはわかりますが、自分の手に余る荷物なら、潔く預けてもらいたいものです。
帰りの飛行機は、久々にスターフライヤーを利用しました。以前、単身赴任をしていた頃によく使っていた航空会社です。新しい機体に更新されているようでしたが、雰囲気は変わっていませんでした。乗り込んだ瞬間、一仕事終えて家に帰るときの開放感と、まだ幼かった息子と別れて赴任先へ向かった寂しさとを思い出しました。もっとも昨日は息子と一緒。飛行機で移動するのが好きなようで、窓側席を満喫していました。私は選べるならいつも通路側。狭苦しい思いをするのが苦手なので、飛行機では通路側を選ぶようにしています。
経営者に持ち上げられてはいけない
中小企業支援をしていると、「先生」と呼ばれたり、あれこれ持ち上げられたりします。こういうときに調子に乗ってしまうと、いつまでもふわふわと地に足がつかない状態になってしまいます。だから「持ち上げられてるな」と感じたら、足元をしっかり見つめ直すことが必要です。
私は顧問先の経営者に「先生」と呼ばれても、やめてもらうようお願いしています。「岡田さん」と呼んでもらえればそれで充分です。先生なんて呼ばれてしまうと、まるで自分の方が立場が上だと勘違いしてしまいます。経営に向き合っている経営者に敬意を表すためにも、名前で呼んでもらうようにしているのです。
ある専門家の振る舞いが強烈な記憶に残っています。電話をかけた時に名前を相手に聞き取ってもらえなかったようで、「俺の名前がわからないのか!」と怒り出したのです。その人物は界隈ではそれなりに有名な人でしたが、持ち上げられすぎて自分を見失っていたのでしょう。「俺の名前がわからないのか」なんて、まるで小説に出てくるようなセリフでした。本人は真面目だったのでしょうが、周りから見ていれば衝撃的で、さらには滑稽でもありました。

身軽に移動したいものです
従業員を持ち上げる
家業の代表取締役を務めていたとき、従業員とのコミュニケーションの一環として絵はがきを送っていました。売上予算を達成したり接客を褒められたりした従業員に、一言メッセージを添えて送っていたのです。最初は恐る恐るでしたが、悪い反応はなさそうだと分かると隙間時間を使って送るようになりました。
全国に拠点があったので、すべての従業員と十分に会話することはできませんでした。その代わりのコミュニケーション手段という位置付けです。良さそうな絵はがきを見かけると買い溜めしておき、移動中などにせっせと書いて社内便で送っていました。
従業員に媚びる必要はありませんが、同じ社会人同士としての敬意は持たなければなりません。面と向かって話せなくても、手紙は一定の役割を果たしてくれます。究極のアナログな手段ですが、喜んでくれた人が多かったのは今でも心に残っています。
人は誰しも褒められたいもの。このことに老若男女は関係ありません。素直に持ち上げれば、喜んでくれる人ばかりのはずです。小言を言いたくなる口元をぐっと押さえ、まずは日頃の感謝を伝えることから始めましょう。
秋から働き方が変わるので、また絵はがきを買い込んでおこうと思います。
関連記事