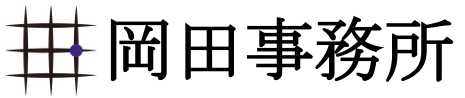飲みすぎた後に考えたこと

ひさびさに二日続けて飲み会に参加してしまいました。最悪の二日酔いは回避できたものの、それでもうっすらと頭痛を抱える羽目に。飲酒について書いてみます。
2日続けて飲んだ
送別会らしきものが続いていて、一昨日は結構な量を飲酒しました。飲んだのはビール、レモンサワー、日本酒、そして再びビールといった感じ。特に日本酒を飲み過ぎたのが誤算でした。ただし、帰宅してから事前に用意しておいた経口補水液とバファリンを飲んだせいか、二日酔いは軽度で済みました。そして昨日も飲み会で、ビールとハイボールを少し。普段はまったく飲まないので、二日続けての夜遊びは体力的にすっかり消耗してしまいます。
あと一か月ほど飲み会が続き、連日の予定も入っています。飲み過ぎないことが一番ですが、帰宅後の水分補給を忘れないようにしなければいけません。私の場合は脱水症状に伴う頭痛がひどくなりがちなので、とにかく水分を摂ってから寝るのが大事。その時は喉が渇いていなくても、経口補水液パウダーを溶いた水を飲んでから寝ればなんとかなる、というのが最近の二日酔い対策です。
たまにまったく二日酔いにならない人がいますが、私からしたらうらやましい限り。二日酔いにならないのであれば、いくら飲んでも問題ありません。おそらく体質の違いなのでしょう。自分の体質をよく理解して楽しむのが大事です。
飲んだら乗るな
JALの機長飲酒問題 「聖域」に経営陣も踏み込めず
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC175RX0X10C25A9000000/
「(パイロットが属する)運航本部は専門職の集団。経営陣でも入り込んで意見を言うのが難しい」そうです。安全運航に関わる飲酒に関しても規定の遵守を徹底できないような労使関係って健全だとは思えず、おかしな文化の会社だなと感じてしまいます。パイロットに対し適切な処遇をするのは当たり前だとしても、それが既得権益になってしまっては問題あり。経営破綻前からのものなのか、その後の経営再建の過程で生まれたものなのかはわかりませんが、経営のガバナンスがまったく利いていない一つの証左でしょう。
大勢のパイロットを雇用していれば、一定の割合でアルコール依存症の人も在籍しているはず。その前提に立って仕組みを構築しないと、いつまでもこうした不祥事が続発するのではないかと思います。
以前に自動車通勤をしていた時は、前日の夜にたくさん飲んだら家族に送ってもらうか、JRで通勤するようにしていました。昔であれば二日酔い運転で済んでいたとしても、今では立派な飲酒運転になってしまうから。私と一緒に飲んでいた知人が朝の点呼でアルコールチェックに引っかかったと聞いたこともあるので、まさに運転できる状態ではなかったでしょう。「飲んだら乗るな」は翌朝も徹底しなくてはいけない時代になりました。

普段はまったく飲みません
飲酒以外のコミュニケーション手段を作る
家業の代表取締役を務めていた時、「飲むのも仕事」と言い放ち、週の半分くらいは飲み歩いていました。実際にコミュニケーションを深めるためには決して無駄ではなかったのですが、まだ30歳前半の若いころだからできたことでしょう。秋から働き方が変わってまた同じように飲むかというと、おそらく無理。以前のように自動車通勤をすることもあって、お酒を飲む機会はそれほどなさそうです。
自分が何者で何を考えているかを知ってもらうには、飲み会というオフタイムを利用できないのであれば情報発信一択でしょう。この3年間取り組んできたブログ、メルマガ、ポッドキャストでの経験を生かすことができそうです。飲酒もコミュニケーション手段の一つですが、もはや当たり前のように多くの人が参加する時代ではなくなりました。仕事を終えたらさっさと帰るのが時代の流れ。経営者は飲酒以外のコミュニケーション手段を用意しなければなりません。
顧問先のある企業では会議のたびに、全国各地に散らばっている従業員さんを本社へ呼び戻しています。このことを知った時に思ったのが、会議なんかよりもバーベキューをした方が良いのではないかということ。会議は何かを決める場ですが、数字の確認とできなかった理由の追及で終わってしまっている会社がほとんど。そんなことだけで一日を終えるのではなく、会議の後にバーベキューをした方が一体感の醸成や経営者の考えを伝えることに役立つのではないかと思ったのです。
関連記事