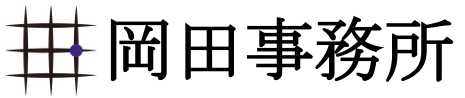ビジネス書の読み方

普段は小説ばかり読んでいて、どうしてもの時だけビジネス書を読むようにしています。
Kindleのハイライト機能で線を引く
基本的にビジネス書を乱読することはありません。うさん臭い本が多いのと、読み物としてつまらないからです。私は基本的に小説が大好きで、常に何かの小説を読んでいないと気が済みません。そんな私がビジネス書を手に取るのはどうしてもの時だけ。その時考えていることに役立ちそうな本と出会えば目を通すことにしているのです。
今も同じ。秋から働き方が変わるのに備えて考えていることがあり、その方針が間違っていないかをビジネス書を読みながらさらに検討しているところです。この本の書名はそのうちにお伝えすることになると思いますが、以前に家業の代表取締役を務めていた頃の私と同じような行動を奨励しているので感覚的には読みやすい本です。読み進める度に感動を得られるような性質のものではありませんが、初めて地方中小企業の経営に携わろうとする人にお勧めできそうです。
ビジネス書を読む時は、Kindleアプリで読みながらハイライト機能で線を引くことにしています。こうしておけば後から振り返って、自分がどんな点を学んだかを振り返ることが可能になります。ビジネス書を読む目的は読み物として楽しむのではなく、経営を学ぶため。漫然と読み進めて良かった悪かったで済ませるのではなくて、何かを得ようと食いつく姿勢が必要です。
実践しなければ意味が無い
さらに言えば、ビジネス書は読んだ後が重要で、一部または全部を経営で実践する必要があります。ただ通読しただけでは時間を浪費するだけになり、経営の現場で実践することで初めて価値が生まれます。
そう考えると、流行のビジネス書に飛びつくのは考えものです。その瞬間の話題にはなっているかもしれませんが、どこまで商売の現場に役立つかはまだ多くの人が試していないはず。話題先行型のビジネス書に振り回されてしまっては経営資源を浪費することになります。そのため私が読むのは基本的に有名なビジネス書ばかり。ただでさえ小説を読む時間を割いているわけですから、時間を無駄にしたくないのです。
古典として生き残っているビジネス書であれば、ハズレである確率は低くなるはず。さらに多くの経営者の実践に耐えうるだけの実証がなされているはずなので、自分にとっても有用であることが期待されます。
ある経営者の本棚にはそれらしいビジネス書が何冊も並べられていました。私が読んだことのある本も数冊混じっています。この経営者と話しているとたくさんのことを学んでいる気配が感じられるのですが、あくまで気配止まり。「行動量」があまりにも少ないのです。営業しない、情報発信しない、改善しないといった具合で、いつまでも以前の自分から変わろうとしません。せっかくビジネス書を本棚に並べているのであれば、どれか一冊を手に取ってとことん実践してみればいいのに。
ビジネス書は実践してみて初めて価値を生み出します。

古本屋巡りにも憧れます
読むスピード
私の場合、ビジネス書を読むスピードは小説よりもだいぶ遅いです。一文ずつ噛みしめるように読み進めて、必要であればハイライト機能で線を引くのでどうしてもゆっくりしたペースになってしまうのです。小説であれば一気に読み進めることができるのに、ビジネス書の場合はそんなことできません。今読んでいる本はようやく25%。早く読み終えて新しい小説を読みたいです。
次に読もうとしている小説はいくつかって、「夜は短し歩けよ乙女」森見登美彦、「罪の轍」奥田英朗、「華氏451度」レイ・ブラッドペリ、「南海王国記」飯嶋和一などです。たまにビジネス書を読むと、その後に反動のように小説を読み漁ることになります。どれだけビジネス書が嫌いなんだよという話ですが、仕事柄、どうしても目を通さなければならない時があるので我慢することにしています。
反Amazon法のフランスに学べ 出版危機の日本、重い「公共財」の覚悟
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR30BHF0Q5A630C2000000/
先日の日本経済新聞にこんな記事がありました。「フランスは本を国民の「公共財」と位置づけ、政府が出版業界に積極介入する」そう。政府の補助金で開業・運営する街の独立系本屋もあるのだとか。私は本は好きだけれども、紙の本はあっという間にスペースを占有するので手に取らなくなってしまいました。電子書籍を買える本屋なんてあるのでしょうか。
関連記事