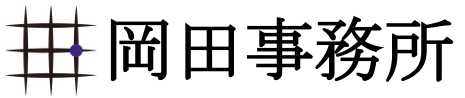会社は経営者の器以上に大きくならない

従業員などのメンバーの能力ばかりが問われがちですが、経営者の資質も重要なはずです。
経営者に退任を促したことがある
ある本を読んでいたら、会社に参画するメンバー選びで妥協してはいけないと書かれていました。製品やサービスづくりに失敗しても、人さえ優れていればどうにかなると説くのです。では、取締役会メンバーや従業員の採否を決められるのが経営者だとすると、経営者自身の資質は誰が判断すれば良いのでしょうか。
ある企業は優れた技術を持ちながら営業力に乏しく、社会実装に至らないまま廃業を余儀なくされました。創業メンバーは営業に注力しようとしない経営者に愛想を尽かし、次々と去っていき、最後には経営者一人しか残らなかったそうです。もしこの会社で経営を他の人に任せていたら、結果は違ったかもしれません。大学発ベンチャーというだけで持てはやされる風潮もありますが、技術があっても経営者に資質が欠けていれば、いずれ立ち行かなくなってしまいます。
創業まもない会社やオーナー企業の場合、経営者の進退は自分で決めるしかありません。この時、自身を過信する人が経営者であればまさに悲劇。能力に欠けているのに経営に携わろうとしてしまうわけで、本人以外にとっては悪夢です。結局のところ、自分の能力とセンス、そして今この局面で自分が経営者にふさわしいかどうかは、本人が見極めるしかありません。
私自身、ある経営者に対して退任を促したことがあります。心身の不調を打ち明けられたこともありますが、明らかに能力不足でした。ビジネス書は読み漁っているのに行動が伴わず、目先の作業ばかりに没頭してしまうタイプの人だったのです。
心身の不調を理由に退任すれば、いろいろ丸く収まったはずです。しかし、ご本人は経営者の椅子を手放すことに大きな抵抗を感じ、続投を選びました。結果、この企業も実質的に廃業することに。もしあの時、誰かに経営のバトンを渡していたらと今でも悔やまれます。
事業承継の経験者として
私は父から事業承継をしています。既に業績が悪化していた家業の経営者を交代するように、メイン銀行から遠回しに意思表示があり、それを受けて父が私に事業承継を打診してきたのです。
当時、私は初めての管理部門の係長をしていました。係長といっても部下はなく、取締役や部長の仕事を手伝う見習いのような立場。そんな状況でいきなり代表取締役になるよう言われたのですから、驚かないはずがありません。
もちろん家業でしたから、いつかは事業承継するつもりでした。しかしあまりに唐突で、状況も最悪。実質的に銀行の管理下にあり、経営的にも身動きが取りづらい状態でした。それでも受けることにしたのは、それが自分の役割だと考えたから。思い描いていたような承継にはなりませんでしたが、緊急時に果たすべき役割があると開き直ったのです。
その後5年間、代表取締役を務めて最後は投資ファンドへ事業譲渡することになりました。操縦不能の飛行機をなんとか着陸させようとするような経営でしたが(飛行機を操縦したことはありません)、資金繰り破綻という最悪の事態だけは避けられました。
この結末をどう評価するかは人それぞれです。投資ファンドに会社を取られた「バカ社長」と見る人もいれば、祖父から数えて3代目が会社を倒産させたと見る人もいるでしょう。逆に「あの状況でよく軟着陸できた」と言う人もいます。江戸時代から続く家業の経営者としての資質がどうであったかは、それぞれ好きなように評価してもらえれば良いと思っています。

さて自分の器のサイズはどれくらいでしょうか
中小企業支援の不都合な真実
中小企業支援の不都合な真実の一つに、「支援が成果を約束しない」というものがあります。公的支援機関の支援メニューをフルに活用したからといって、名だたる大企業のように成長できる保証はありません。
突き詰めれば、経営者の資質こそが成長の可否を左右します。しかし、このことをはっきり指摘できる人は少ないのが現実です。私が元茶わん屋だから言うわけではありませんが、「会社は経営者の器以上に大きくならない」というのはまさにその通り。事業が成長するかどうかを見極めたいなら、経営者の目を見れば良いのです。
そういう私も、この秋から働き方が変わり、どなたかに目の色を見定められる立場に戻ります。次の挑戦に備える日々を送っています。
関連記事