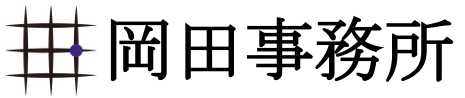四万六千日

妹が浅草に行ったと聞いて、ある落語の演目を思い出しました。
落語「船徳」
落語に「船徳」という演目があります。勘当された若旦那が船頭になり、浅草の四万六千日(しまんろくせんにち)の縁日の日にお得意様を乗せて大騒ぎになるというあらすじです。私は勘当されたことはありませんが出来の悪い三代目(祖父から数えて)と呼ばれていたことはたしかで、どこかわが身を重ねてしまう演目です。さらにいえば、若旦那が船頭になったように私も大型二種免許を取得しています。まだサラリーマンだった頃に、いつか会社から追い出されても最低限食べていけるための資格を取っておこうと教習所に通いました。
卒業検定以来、大型バスを運転することなく社会人人生を歩んできています。元々バスが好きだったので、今でも選べるのであればバスで移動するようにしています。最近よく見かけるのが、運転手が不足しているせいか、私と同じような年代の方が先輩の指導を受けながら運転している姿です。おそらく転職したばかりの運転手さんが、丁寧に運転している様子は思わず応援したくなります。
大型バスというと運転が難しそうなイメージを持つかもしれませんが、実際にはそんなことなく、ゆったり運転するコツさえ掴めば快適なものでした。当時から乱視気味だったせいか車庫入れの練習に苦戦したくらいで、教習自体は楽しくあっという間に終わってしまったのを覚えています。
先日、バスに乗っていたら、時間を合わせて運転手さんの家族が乗り込んできたようで、お嬢さんがうれしそうに一番前の席に座り、お父さんが運転する様子を眺めていました。それだけの出来事だったのですが、なぜだか私までうれしくなってしまい、いつもより大きな声で「ありがとうございました」と言ってバスを降りました。
熱中症
その四万六千日の縁日に合わせて、東京に住む妹が浅草へ行ったそう。浅草寺の境内で開催されていたほおずき市が目的で、日傘にサングラスと完全武装していたのに熱中症気味になってしまったと連絡がありました。
妹というと私より年下なわけで(当たり前ですが)、熱中症なんかにはなりにくそうなイメージでしたが、彼女ももう今年44歳なので昔のような体力は無いようです。つまり、私もそれだけ年を取ったということ。つい、アマチュア無線をするために低い山へ登ったり、日を遮るもののない展望台で交信を試みたりしていますが、本当に気を付けないと危険だなと思い知らされました。
高校のボート部で学生コーチをしていたことがあり、天候を理由に練習を中止させたのは雷の時くらい。真夏の暑さは帽子と冷たい飲み物でどうにかなる時代だったので、まさか気温が上がりすぎたからと運動を思いとどまらねばならない時代になるなんて思ってもいませんでした。
ある顧問先では空調服を導入してもらっています。当初は「大げさな」といった反応だったのですが、今では普通に着用して作業してくれているそう。熱中症対策は現場から要望が上がってくる前に、経営側が先回りしなければいけないと思っていて、早めに空調服を導入してもらえたのは正解でした。現場はどうしても従来通りのやり方を踏襲したがるものです。そんな時でも多少の軋轢が生じるのを恐れずに、判断すべきは判断しなくてはいけないと再認識した出来事でした。

そういえば小さい頃に祖母と行ったことがあるかもしれません
四万六千日分のご利益
四万六千日になんでわざわざお参りするかというと、この日にお参りすれば四万六千日分のご利益があるからだそうです。通常日よりも46,000倍の効果が得られるなんて、なにかの設定を明らかに間違えているように思えてしまいます。だからこそ熱中症になる危険を冒してでも妹は向かったのでしょう。
ある経営者は他社の取り組み事例、要は他社の成功事例ばかりを聞きたがるので対応に困っています。成功事例を同じようになぞれば楽をして儲けることができると信じているようで、私と顔を合わせると事例ばかりを聞きたがります。そうした事例の表面上の部分だけをなぞろうとする行為は無意味だと思っていて、「事例なんか気にする前にドブ板営業をしてきてください」などとお伝えしています。
経営に勝利の方程式や魔法の杖、もしくは四万六千日のようなボーナスステージなど存在しません。地に足を着けて見込客と向き合った者だけが売上を得られるのです。凡事徹底、商売に奇策なし、です。
ポッドキャスト「茶わん屋の十四代目 商いラジオ」を毎週金曜日10:00に配信しています
関連記事