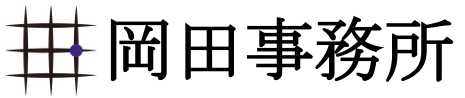人前で話せるようになった理由
人前で話すのが最初から得意な人などなかなかいないでしょう。私は手も足も震える性格でしたが、今ではなんとなく普通にしゃべれるようになりました。自分なりのポイントをまとめてみます。
取引先を集めた新年会でのスピーチ
人前で話すのはずっと苦手でしたが、何度も恥をかいて最近では下手なりに話せるようになっているつもりです。仕事で最初にスピーチらしいスピーチを求められたのが、家業の代表取締役を務めていた際の新年会。取引先を集めてホテルの宴会場で開催していたのですが、冒頭に直近の状況などをお話しすることになっていました。当初は何を話してよいやらまったくイメージが掴めませんでしたが、初売りの状況などを数字を交えてお伝えし、新年も継続してお取引いただくようにお願いするスタイルに落ち着きました。
私が心がけていたのは意気込みだけでなく数字もお伝えすること。ぼやっとした話だけで「応援してください」と言っても思いが十分に伝わらないと考え、リアルな数字を織り交ぜて説得力を持たせるようにしました。どの数字を伝えるかも重要で、その時々のトピックの中からふさわしいものを選び出していました。「数字で語る」というのは金融機関に出向く時も心がけていたこと。商売の結果は数字で表れるものなので、その数字を私が(ある程度)把握していることを示すようにしていました。
当時は一言一句を記した台本を用意し、直前に丸暗記するスタイル。ぶつぶつと一人で呟いて練習してから本番に臨んでいましたが、たまに覚えていたことが飛んでしまうことも。ある時から中途半端にメモを用意するから暗記が必要になることに気づき、それ以来、箇条書きで概要だけを書いておき、ステージに立つように変えました。
講演
中小企業支援家に転身してからは、江戸時代から続く家業を投資ファンドへ事業譲渡した経緯や、事業者と共に取り組んだ中小企業支援事例をお話しする機会をもらえるようになりました。少人数が対象の勉強会やホテルの宴会場で実施するような講演など、年に数回程度。頻度は少なくても私にとっては貴重な機会で、人前で話すためのトレーニングにもなっています。
一番最初の機会は某省庁での勉強会でした。霞が関の官僚向けにA4一枚にまとめた資料を元に15分ほどお話ししました。今から振り返るとあの資料でどこまで何が伝わったのかはまったく心もとないですが、当時はそれなりに反応があり、自分の体験がコンテンツになるのだと気付くきっかけになりました。
講演で話す際にはパワポ資料を投影しながら話します。資料はその都度、手を加えていて、反応が良かったところ悪かったところ、話しやすかったところ、話しづらかったところなどを講演後に振り返っています。徐々に洗練されてきているはずですが、洗練されすぎると話の臨場感が失われることもあります。専業の講演講師ではありませんので、適度な素人感は残したほうが良さそうです。
パワポ資料では発表者ツールのメモを利用することはありません。一言一句を記してしまうと読み上げるだけになるので、その場の雰囲気に合わせて強弱をつけるためにも、台本は用いません。
これまで何度も機会をいただいた家業での経験を話す講演も、今後は減らしていくつもり。事業譲渡から10年が過ぎて、いつまでもこのコンテンツにしがみつきたくないという思いがあるからです。十年一昔とはよく言ったもので、今後は継続の案件以外はお受けしない方向です。
自分で自分を演じる
私の経験からすると、人前で話すのに慣れるためには場数が必要。当たり前と言えば当たり前ですが、実地に経験しないことには心に余裕が生まれることはありません。また一言一句を暗記し、完璧なパフォーマンスを披露しようというのも荷が重いもの。その時に話したい内容を箇条書きにしておき、万一、頭が真っ白になってしまってもその箇条書きを読めば何を話すつもりだったのか思い出せるようにしておくのがお勧めです。
人前で話すというのは自分で自分を演じるようなもの。どこかの百貨店のバックヤードから売り場への入り口に、「ここから先は舞台です」みたいな貼り紙がされていたのを見かけたことがあります。つまり売り場では販売員を演じてくださいということ。普段の自分よりもギアを一段か二段上げるくらいが、仕事でどなたかと接するのにはちょうど良いのでしょう。人前で自分を演じる時も同じ。いつもより少し声を元気に、いつもより身振りを大げさにするくらいがちょうど良いのです。
ポッドキャスト「茶わん屋の十四代目 商いラジオ」を毎週金曜日10:00に配信しています
関連記事