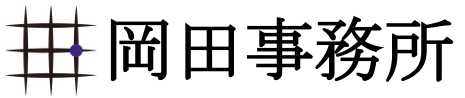真の強みを生かした経営戦略を持っているか

地方中小企業の経営者とお話ししていると、自社の真の強みを理解し、経営戦略に反映させている人はそれほど多くないように感じます。そもそも経営戦略とは何でしょうか。私が考える経営戦略について書いてみます。
会社全体がゆでガエル状態になっていないか
ある会社で話していると、売上は減少傾向が続いているそうで、またこの先も仕入に重大な支障が生じる見通しだということがわかりました。ここまで先を見通せているのに、未来への明確な打ち手は無し。経営者以下、誰もが昨日と同じ仕事を繰り返し続けています。まさに会社全体がゆでガエル状態になってしまっていて、予算比・前年比90%台は当たり前で成長どころか現状維持すら覚束ない状態です。
この会社の経営者に対して申し上げたのは、雇われる立場の人々に引きずられて思考してはいけないということ。従業員がゆでガエル状態になってしまっていたとしても、経営者はただ一人、未来への打ち手、つまり経営戦略を考えなければならないのです。経営戦略とは、「企業あるいは事業が稼ぎ続けるための独自の立ち位置を築く計画」だと考えています。刹那的な売上を作るだけなら誰でもできることですが、大事なのは将来に向かって稼ぎ続けることで、さらにその仕組みが競合に安易に模倣されないように企図することです。
いまその会社では経営者自らが新規事業に取り組み始めています。自社の真の強みを理解し、その強みをテコに市場へ新たな価値を提供しようと駆け回っています。今のところどうやらその方向性が間違っていないようだと確信しつつあり、今後さらに投資を重ねていく予定。既存事業の売上が減少傾向なので、会社が息絶えるか、その前に新規事業が新たな売上の柱に育つかの競争です。この危機感を正しく理解できているのは会社で経営者ただ一人。それでも前を向いて行動しなければいけないのが経営者なのです。
それらしき戦略を掲げるが行き当たりばったり
ある経営者は戦略らしきものは持っているのですが、その時々でコロコロと変わります。ある時は数を追いかけ、しばらく経ってうまく行かないことがわかると質を追うといった感じ。そこに思考の軸は無く、場当たり的な行動をしているだけのように見えてしまいます。
繰り返しになりますが経営戦略とは、「企業あるいは事業が稼ぎ続けるための独自の立ち位置を築く計画」です。ただの計画ではなくて、独自の立ち位置を伴う必要があるのがポイント。売れそうだからA、売れなかったからやっぱりB、などと定めるものではありません。
逆に言うと、いつまでも経営戦略が定まらないということは、独自の立ち位置を築くための真の強みを持ち合わせていないということかもしれません。強みがなければ競合と不毛な争いを強いられ続けるわけで、そこに持続可能性は存在しません。もし経営戦略を策定できないのであれば、市場から退場することも選択肢に入れるべきでしょう。

カエルを茹でてはいけません
自分の真の強みを理解している人は少ない
ある会社の真の強みを私は、「海外での生産管理能力」だと理解しました。でも当の本人たちにとっては当たり前のことで、私が何度言ってもいまいちピンと来ない様子。周りからそれらしい商談が持ち掛けられても、自分の真の強みを認識できていないのでどこか的外れな対応をしてしまいがちです。
経営者と対話する際にはその会社の真の強みを見い出そうと努めるわけですが、すぐに理解できることもあれば、何回か対話を重ねてようやく見い出すこともあります。どちらの場合でも次はその真の強みを生かすこと、つまり経営戦略の立案に話題が移っていきます。
経営戦略というと小難しい計画を思い浮かべるかもしれませんが、本来はごくシンプルなものであるはず。シンプルだけど他社が安易に模倣できない要素が埋め込まれていることで、強固な稼ぎ続ける仕組みとすることができるのです。小難しい計画は文字や数字を弄んでいるだけ。本当に強い経営戦略は、ほんの数行で説明できるものであるはずです。
ちなみに中小企業支援家である私の真の強みは、「江戸時代から続く家業を投資ファンドへ事業譲渡した経験があること」です。実際に地方中小企業を経営していた支援者なんてほとんどいませんし、江戸時代から続く老舗を事業譲渡した経験がある人も同様。地方中小企業の経営経験があり、さらに事業譲渡を経ているからこそ、多くの経営者が私を面白がってくれるのだと理解しています。
ポッドキャスト「茶わん屋の十四代目 商いラジオ」を毎週金曜日10:00に配信しています
関連記事