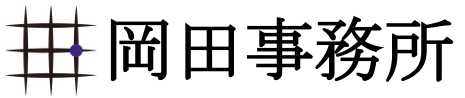経営者はAIバカになるな

さっそくAIに思考を乗っ取られている人をちらほら見かけるようになりました。自分で何も考えずに、AIが生成した情報を無条件で受け入れてしまうのです。地方中小企業の経営者がAIを使う際には、どのようなことに気をつけたら良いでしょうか。
AIは思考・行動するための道具
先日iPhoneのアップデートがあって、Appleインテリジェンスが実装されました。まだAIをフル活用するような先進的な機能は盛り込まれていない印象で、絵文字や画像を生成したり、Siriの発展版のような機能に留まっている印象です。もちろん、今後さらにAI関連の機能は充実していくことでしょう。今の時点で私は、ChatGPTのアプリの方を使う機会が多そう。今後iPhoneがどのように進化していくのか、そもそもiPhone自体が存続するのかも含めて興味深い時期に差し掛かっているように感じます。
ChatGPTやAppleインテリジェンスを使うだけで何かがなされる事はなく、AIは人間の思考・行動を促すための道具に過ぎません。こんなことは当たり前なのですが、AIをいじっているだけで何かを生み出しているように錯覚している人が増えているように感じます。
思考・行動しない経営者に未来はなく、事業の持続可能性を担保することはできません。AIは思考のヒントを与えてくれるものですが、経営者に代わって思考してくれる事はありませんし、もちろん経営者に代わって一歩を踏み出してくれるものでもありません。AIは、あくまで道具。このことを肝に銘じ、くれぐれもAIに振り回されることのないようにしたいものです。
良質なインプットの存在がAIを使う前提となる
AIがライターに代わって文章を、さらにはカメラマンに代わって画像を生成してくれるようになりました。そうした成果物を業務に使用できる機運は徐々に高まっていますが、果たしてすべてが業務に耐えうる品質のものなのかどうか。この判定を下すことができるのは感性を持っている人間だけで、AIが生成したものだからといってそれだけで飛びついていては、品質の低さを顧客に笑われることになりかねません。
AIが生成したものを使いこなすには、人間がセンスを養っておく必要があります。そのためには、日ごろから良質なインプットを続けておかなければいけないのは、AI登場以前と変わるものではありません。例えば、ウェブサイトに使うバナーを用意するとしたら、イケてるもの、イケてないものを即座に判断できるセンスが求められます。そうした感性を持ち合わせていなければ、外注先のデザイナーさんにイメージを伝えることすらままならないはず。審美眼を養っておかなければ、物の良し悪しを伝えたり判断したりすることはできないのです。
私にとって貴重なインプット源は日本経済新聞です。新聞に書いてあることが常に絶対正しいなどとは考えていませんが、それでもうさん臭いネットの情報などからしたらはるかに正確であるはず。元茶わん屋の私が業種関係なく多くの経営者と対話できているのも、日頃から新聞を読んで広く浅く世の中の情報を仕入れているからでもあります。新聞離れが進んでいると言われますが、こんなに良質なインプット源が人々の支持を失いつつあるというのはもったいないことです。私にとって月々数千円の購読料はもっとも効率の良いお金の使い方です。

AIに振り回されないように生きましょう
そこに覚悟を持てるのか
経営の現場で言えば、選択肢を洗い出した上でどの道を進むか決めるのが経営判断です。AIが提案したからといって何も考えずに飛びつくのか、提案された選択肢を吟味し自らの意思として経営判断を下すのか。もちろん望ましいのは後者。AIなんかを神様のように信じてしまうことなく、材料のひとつとして使って経営判断をし続けなければいけません。
経営者として持つべきは覚悟。AIを使って下したその判断に覚悟が伴っていればよし、覚悟から逃れるためにAIを使っているのであれば経営者失格でしょう。誰もが不確かな将来に向かって少しでもマシな未来を生み出そうとあがいているなかで、経営者には覚悟が求められます。
経営者とは弱い存在。ありもしない経営の解を教えてくれる「魔法の杖」や、安直なビジネス書にすがろうとしてしまうくらいです。そんな彼ら彼女らにとってAIは危険な道具にもなり得ます。AIは大きな可能性を秘めていますが、思考・行動しない経営者まで救ってくれることはありません。まずは自分の頭で考え、一歩を踏み出しましょう。
ポッドキャスト「茶わん屋の十四代目 商いラジオ」を毎週金曜日10:00に配信しています
関連記事