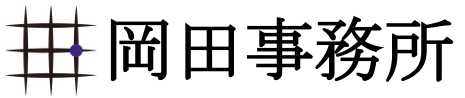最近購入した本(2025年3月)

読み終えていない本がいくらでもあるのに、今月も何冊か購入してしまいました。どんな本を買ってしまったのか紹介してみます。今読んでいるのは司馬遼太郎「街道をゆく」の第3巻。たまにこうした紀行文を読むのも新鮮で楽しいものです。
小隊 砂川文次 文藝春秋
福岡に住んでいるとアジアに近いこともあって、この国はいつまで平和でいられるのだろうと考えることがあります。政治の話をするつもりはありませんが、人類の歴史は戦争の繰り返し。この先、戦争のない平和な日本が続くというのはどうやら難しいのではないでしょうか。今が平和だと言ってもせいぜい80年くらいの話。日本史や世界史の教科書を思い出したら、80年なってほんの一瞬です。たまたま戦間期に生きているだけであって、何かが目の前に迫ってきているのかもしれません。
先日、NHKオンデマンドでロシアに攻め込まれたウクライナの開戦当初の様子を伝えるドキュメンタリーを観ました。どこまで真実を伝えている番組なのかというのはともかく、どうやら市民が立ち上がって危機を乗り越えたことは確かなようです。同じようなことが日本で起きた時に、何がどうなるのでしょう。
まったく話は変わりますが、アマチュア無線が災害時に役立つとのことで、日頃から訓練に励んでいる人々がいるそうです。一度誘ってもらったことがあるのですが、私の非力な無線機では参加できそうにないのであきらめました。戦争や災害はいつか必ずやってくるもの。備えよ常に、です。
#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった 大塚あみ 日経BP
私は常に何かを読んでいないと落ち着かないくらいなのに、息子はどうやら読書にそれほど関心が無い様子。長い春休みを過ごしている彼の何かの刺激になればと買ったのがこの本です。といっても私が読んだわけではなくて、日本経済新聞の広告で気になっただけ。本人が読まないのであれば、私が読むことにします。
こうして息子に本を渡していますが、私は誰かから本を勧められるのが苦手です。何かを押し付けられるような気がして、まったく読む気が起きないのです。本って読んでいる瞬間よりも、次に何を読もうかと選んでいる時間が楽しいのです。小学生の頃、自宅近くの本屋へ行っては長い時間本を選んでいて呆れられたことがあります。立ち読みする勇気はありませんでしたが、背表紙を眺めてどんな本かを想像し、その日に買って帰る本を選ぶだけでわくわくできたのです。
この本は毎日連続で100本のアプリを作った話が書かれているそう。100日連続と聞くと、私は情報発信をしようとする事業者へ、「まずは100回発信しましょう」と促すことにしています。一日、二日の発信で何かが変わることなんてありえなくて、多少のクオリティのばらつきがあったとしても100回取り組めば勘所が掴めるのではないかと考えているからです。
ちなみにこの本は息子に渡すために紙の本を購入しました。普段はKindle版ばかりを選んでいるので紙の本が届くと新鮮です。未読のKindleも他のユーザーに渡すことができればいいのに。紙の本と違い、いつまでも読むことができるかどうかわからないのがKindleの欠点。でもスペースに限りがあるので、自分の本は電子版以外考えられないようになってしまいました。
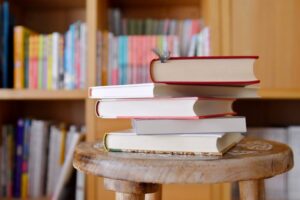
自分の本棚が欲しいです
声の網 星新一 KADOKAWA
許されるのであれば、小説ばかりを読んでいたいです。ただ仕事柄、ビジネス書を読んだり、小説から横に逸れて紀行文を読んだりすることもあります。小説も長編小説ができれば望ましくて、面白い話をできるだけ長い時間楽しみたいと考えています。そのため短編小説は嫌いじゃないけれど、積極的に選ぶことはありません。
ひさしぶりに購入したのがこの星新一の本。短編をいくつか読んだことがあるくらいで、腰を据えて取り掛かったことがないのがこの作家さんです。この本をきっかけに追いかけることになるのか自分でも気になっています。
私が好きな作家は池波正太郎、司馬遼太郎、塩野七生など。Kindleで合本版がセールになっていた時があって、真田太平記、鬼平犯科帳、剣客商売、坂の上の雲、竜馬がゆくなどをここ数年で再読しています。しょうもない流行りの小説を読むくらいであれば、これらを何度も読み直した方が、間違いなく充実した時間を過ごすことができます。
ポッドキャスト「茶わん屋の十四代目 商いラジオ」を毎週金曜日10:00に配信しています
関連記事