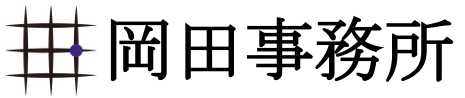地方中小企業の経営者に聞いてもらいたい落語の演目(2025年3月)

最近聴いた落語の演目から商売の学びになるものをいくつか紹介してみます。学生の頃から新宿末廣亭へたまに行っていました。最近になってこうしてまた聴いていると、福岡にも演芸場があると良いのになと思ってしまいます。
唐茄子屋政談
唐茄子とはかぼちゃのこと。商家の若旦那が唐茄子を売り歩くことになり、叔父から商売について諭される場面があります。これまで放蕩三昧でお店のお金を勝手に使っていた若旦那に対し、「従業員が稼いでくれたお金」とその有りがたさを説きます。
家業の代表取締役を務めていた時、ある人から「経費を好きに使えて良いですね」と言われて腹が立ったことがあります。たしかに経費を使おうと思えばいくらでも使える立場でしたが、私が経費を使えばその分、利益が減ります。従業員が現場で茶わんを売って作ってくれた現金を使うからには、理由と成果が必要であるのは当たり前のことです。でも世の中には、中小企業の社長は経費で飲み食いできてうらやましいなどと安直にしか考えられない人もいるのです。
そういえば、経費を自由に使えるのは今も同じ。個人事業主ですので、事業に関わる経費をどう使うか決めるのは自分自身です。こうした仕事をしているので、主な経費は旅費交通費や新聞図書費。カーシェアリングを利用して顧問先へ出向いた時や、経営の参考になりそうな本を買った時は経費として記帳することができます。以前になんでもかんでも経費にしていると思われる個人事業主の方を見かけたことがありますが、何かを勘違いしているような。事業とは関係ない支出を経費にすることはできません。
福禄寿
商家の出来の悪い実子と、真面目に商売に励む養子。母親に金をたかりに来た実子について、養子が「一升の袋には一升しか入らない」と実子を小さい袋に例え、大きな事ばかりしようとしていると指摘します。
中小企業支援に携わっていると「大きな話」ばかりしたがる人に出会うことがあります。自分を大きく見せたいのか、舐められまいと必死なのか。いずれにせよ自分の袋の大きさに見合っていない話であることはすぐにわかってしまいます。人にはそれぞれの袋の大きさがあるもの。まずは自分の身の丈を理解することで、初めて背伸びもできるというものです。
以前に関わった創業を志している人で、「私は稼ごうと思えばいくらでも稼げる」「アフィリエイトでもやれば生活に困ることはない」などと強がっている人がいました。その後、創業したらしいのですが数年も経たないうちに廃業してしまったようです。大きな話ばかりしていると応援してくれている人もそのうちに離れてしまいます。ひょっとしたら、そもそも誰も応援していなかったのかも。わからないことはわからないと言い、間違えたことをしたらごめんなさいと言う。素直な心を持つ人に多くの人が集まり、みんなに支えてもらって夢へ近づくことができると信じています。

唐茄子ってかぼちゃのことだそうです
ちきり伊勢屋
商家の若旦那が占いで余命わずかと宣告されてしまいます。その若旦那が社会貢献を始めるのを手伝う番頭さん。二人の暖かい関係が印象に残った演目です。
私も家業の代表取締役を務めていたときに「番頭さん」がいてくれました。財務や労務の後ろをしっかりと守ってくれる彼がいたからこそ、事業譲渡が実現できたのは間違いありません。事業譲渡を終えた後の年賀状に、またいつか一緒に働きたいと書いてくれたのはうれしかったです。
地方中小企業の経営者とお話ししていると、番頭さんがいない企業は経営者に余裕がなく、常に何かに追われるように仕事をしていると感じられます。目先のことに頭が一杯で、数ヶ月先のあるべき姿も思い描いていない会社ばかりなのです。経営者が実務に追われるようになったら終わりの始まり。番頭さんに今日と明日の業務は任せ、経営者は未来を描くことができれば理想です。
こうして落語を聴いていると、経営に役立つ演目が非常に多いことに驚かされます。私は演目を選んで聞いているわけではなくて、上から順に再生しているだけ。それでもこれだけの数の学びが得られるのですから面白いものです。最近はSpotfyで柳家さん喬師匠ばかりを聴いています。私にとってSpotifyは落語を聴くための道具になりつつあります。
ポッドキャスト「茶わん屋の十四代目 商いラジオ」を毎週金曜日10:00に配信しています
関連記事