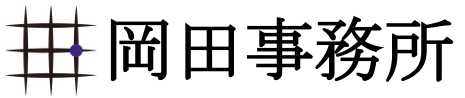SNSは売るための道具ではない

営業と販売は異なります。またSNSは魔法の杖ではありません。そんな商売の基礎を改めて考えさせてくれる出来事がありました。
ある顧問先の経営者が付け加えた意味の無い一言
ある顧問先のSNSをチェックしていて、最近、少し様子が変わったことに気づきました。「オンラインショップはこちら」と購買を促すような文言が必ず付け加えられるようになったのです。SNSは世界観を伝える場にし、売る仕掛けは別に用意するのが我々の作戦のはずだったので、私が抱いた感想は「安っぽい売り込みだな」というもの。直接、「買ってください」と叫んでいるのと同じレベルの心の声を曝け出していて、ブランドの世界観などをせっかく丁寧に伝えていたアカウントの魔法が解けてしまうような感覚を持ちました。
後日、経営者と話す機会があったのでそのことを尋ねてみると、つい売り上げを増やしたくなり付け加えていたとのこと。ただし、効果はゼロ。売り上げに結び付かなかったことはもちろん、その他の数値も向上することはなかったと正直に教えてくれました。そのことに気づいて、そうした文言を使うのはやめたと少しバツが悪そうに話していました。
ここで大事なのは、自分で思考してテストし、効果を見定めて次の判断を下したことではないでしょうか。売上を増やそうと考え、ある文言を使い始めたけれども効果が生まれず、逆効果になりかねないと悟って修正できたのですから。何でもすぐに正解らしきものに飛びつこうとする人が多い中で、こうしたテストを繰り返すのは大事。商売に勝利の方程式なんかなく、自分で正解を作っていかなければいけないのです。
「買ってください」と連呼して売上が増えるなら誰も苦労しない
人は何かを押し付けられることを嫌います。「買ってください」というのも同じ。売り手は売上を増やそうと深く考えずにこうした直接的な言葉を選んでしまうのですが、見込客はストレスを感じるだけで購買意欲を刺激されることはありません。
自分がモノを選ぶ立場であればよくわかることなのに、いざ売り手になるとこの真理を忘れてしまう人が非常に多いです。「買ってください」と連呼して売上が増えるなら誰も苦労しませんし、中小企業支援なんて必要ありません。見込客に自然と選んでもらえるように仕掛けを用意するのが商売の勘所で、売り手の経営戦略の良し悪しやセンスの有無が問われるところなのです。
少し遠回りに思えても、まず必要なのは自己開示です。自分たちが何者で、どんな背景を持っているのかを伝えなければ胡散臭がられてしまいます。個人が特定されないように配慮して自己開示することは十分に可能です。自分が何かを選ぼうとする時に、知っている(つもり)の会社や人を優先していることを思い出してみてください。

「買ってください」は逆効果
営業とは見込客の困りごとを収集する行為
これまた勘違いしている人が多いのですが、営業とは見込客の困りごとを収集する行為のことを指します。何かを売りつけることが営業ではありません。見込客との間合いを詰め、困りごとを打ち明けてもらえるまでの関係性を構築し、その解決手段を提示するまでが営業活動です。
売れた売れないは結果に過ぎません。見積もりがどうとか、支払いがどうとか、納品がどうとかというのは営業ではなく販売。両者はまったく異なります。この営業と販売を混ぜて考えてしまうから、「営業=見込客の事情なんかお構いなしに自社商品を売りつける行為」と勘違いしてしまう人が現れるのでしょう。
そう考えるとSNSで「買ってください」とか「オンラインショップはこちら」などと発信することの無意味さがわかるでしょう。SNSは見込客と出会い、世界観を伝える場のはず。まだ何者なのかもわからない人から売り込みをされても、不快感を抱かれてしまいかねません。
冒頭の経営者は今回の一件を反省材料にし、SNSの役割について再認識することができました。SNSを使うだけで注文が殺到するなんてことはなく、どういった性質の道具であるかを思い出してくれたようです。世の中に溢れている成功事例ばかり眺めているとSNSを魔法の杖と勘違いしてしまいます。いつの時代でも商売の根本は変わりません。まずは見込客の困りごとが何であるのかを見極めましょう。
ポッドキャスト「茶わん屋の十四代目 商いラジオ」を毎週金曜日10:00に配信しています
関連記事