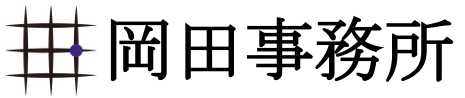異分野のセミナーを拝聴して考えた講演講師の在り方

セミナーを拝聴する機会がありました。参考になることもありましたが、気になったこともいくつか。講演講師の在り方について書いてみます。
情報量が多すぎるスライド
先日、専門外の分野のセミナーを拝聴する機会がありました。参考になったのはマクロの数字から入って、その後に各論を述べていく構成。この分野では当たり前なのかもしれませんが、自分が話すときにも応用してみようと勉強になりました。
一方で気になったのがスライドの情報量です。これでもかというぐらいにグラフや数字が盛り込まれているのに、実際に触れるのはほんの一部だけ。いかにもそれっぽい内容に仕立て上げられていましたが、終わってみれば「何を話していたっけ」という感じ。研究者さんなどに多いのですが、スライドを作るのに無駄に注力してしまい、肝心の伝える能力はやや物足りない印象でした。
ある老舗企業の経営者は何かと資料ばかりを作りたがります。私からしたら以前の資料を流用すれば良いのにと思う場面でも、いちいち資料を作り直していて、まるで資料を用意するのが重要な業務であるかのようです。その割に各スライドは情報量が多すぎて、率直に言って何を伝えたいのかわからないものばかり。ご自身の伝える能力には自信があるようですが、受け手の反応を謙虚に受け止めて改善してほしいとお伝えしたことがあります。
セミナーの目的は参加者に情報を提供すること。見栄え良いスライドや、拡大しなければ読めないスライドを用意することではありません。まずは参加者の困りごとを想定し、その課題解決に資する情報をストレートに提示する姿勢が必要だと思っています。
著作権、大丈夫ですか?
またもう一つ気になったのが著作権の取り扱い。さまざまな媒体からグラフなどを引用していましたが、引用量があまりにも多すぎるような。冷静に資料を眺めてみたら、講師オリジナルの解釈やコンテンツというのがほとんど見当たらなかったと感じたのは私だけだったのでしょうか。
私もグラフや資料を引用することはありますが、あくまで全体のごく一部。拝借した資料ばかりで話していたら、そこにオリジナル性は存在せず、わざわざ私が話すべきコンテンツではなくなってしまいます。講師を依頼されるということは、その講師だから話せることを期待されているわけで、ネットで検索すれば得られる情報を切り貼りしたものだけでセミナーを実施するなんて私にはあり得ない考えです。
さらに「あれ?」と思ったのが、Aiを利用してスライド作成をしているとおっしゃっていて、ところどころ言葉の表現などがぎこちなかったこと。お題だけを投げて、Aiが作成したあらすじに沿って話しているとしたら、もはや講師は人間ではなくてAiです。今後、Ai でできることが爆発的に拡がっていくのでしょうが、リアルの人間が手がけることの価値というのを意識して利用しないと、Aiに思考を乗っ取られるだけです。特にセミナーや講演はその人のオリジナルコンテンツだからこそ価値があるもの。どこかの誰かが同じように話すことができる内容では、謝金をいただくことはできません。

引用ばかりでは「セミナー」とは言えません
講師をしたがる人は多いけれど
講演講師に憧れる人が多いようですが、独自のコンテンツを用意し、さらに常に改善し続けなければいけないとなると、ごく一握りの特殊な経験をした人や有名人でなければ事業として成り立たないと思います。私も年に数回、話す仕事をしていますが、江戸時代から続く家業を投資ファンドへ事業譲渡した体験談をお伝えしているだけ。講演というほどの立派なものではなくて、体験談を伝えているだけという感覚。そのため最近は、「話す仕事」と表現するようにしています。
今どきネットで検索すればほとんどのことは調べることが可能です。そんな時代にわざわざ人の話を聞こうとするからには、ネットやAiに依存しない生々しい情報であることが求められます。それらしい話をするだけなら誰でもできるわけで、独自の強力なコンテンツを持つ人だけが講演講師になれるわけです。
講演講師になりたいのであれば、多くのセミナーを受講してみることをお勧めします。すでに演台に立っている講師が持ち合わせていないような、独自の強力なコンテンツを用意できるのか、そして常に改善し続けることができるのか。もし当てはまるなら講演講師として有望でしょうし、そうでないなら別のことに注力した方が良いでしょう。
ポッドキャスト「茶わん屋の十四代目 商いラジオ」を毎週金曜日10:00に配信しています
関連記事